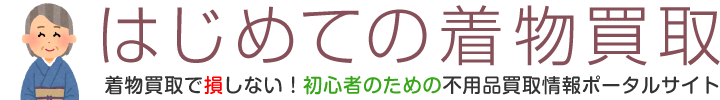新しい住まいへの引越しが決まったら、何から手を付ければ良いのでしょうか。
新居に引越す為に必ずチェックしておきたいポイントと方法を、詳しくご紹介します。
引越しが決まってから、引越し完了までの大まかな流れ

スムーズな引越しを叶えてくれるのが「やるべき一覧を描いた、スケジュール表」です。
ざっくりした流れを分かっておくと「今、何をしたら良いのか」が分かり目標に向かって動きやすくなります。
引越しのスケジュール
■ステップ1) 引越し方法を決める
引越しのスタイルは「自分でおこなうか」「引越し業者にお願いするか」2パターンです。
引越し業者に依頼するときは、いくらかかるのか事前に見積りをお願いしましょう。
■ステップ2) 住まいの「解約」連絡をする
賃貸住居に住んでいる場合、退去日がわかった時点で、管理業者やオーナーさんに早めに連絡を入れましょう。
■ステップ3) 荷作り&引越し前の手続きをする
自分の荷物は少ないように見えても意外と多いもの。「捨てるもの」「新居に持って行くもの」とテキパキ分けながら荷作りを進めていくことが大切です。
また荷作りと同時におこないたいのが、引越し前の手続き。
自治体への「転居届」、ライフライン関連の住所変更「電気・ガス・水道・インターネット・固定電話・携帯電話・新聞・銀行」、お子さんがいる場合は「転園・転校」などの届け出が必要になります。
■ステップ4) 引越しの当日、荷物を搬出する
引越し当日は、あっという間に時間が過ぎていきます。慌てないためにも、何をするのか事前に整理しておきましょう。
■引越しの当日の流れ
- 引越し業者の到着
- 搬出作業がスタート
- 料金の支払い
- 部屋の最終チェック&掃除
- ※管理会社の立ち合い、鍵の返却
- (※後日におこなうケースもある。)
- 新居に向かう
■ステップ5) 引越しが終わる、荷ほどきをする
新居に着いてからも、やるべきことは山ほどあります。荷ほどきと同時に、自治体への手続き・ご近所の挨拶まわりなどをサクサク進めていきましょう。
■ステップ6)引越し後にやること
- 荷ほどき
- ガスの開栓立ち合い
- 自治体へ転入届の提出
- 運転免許証の住所変更
- 知人に「転居のお知らせ」ハガキ
- ご近所へ挨拶まわり
それぞれ、詳しく紹介していきます。
ステップ1:引越し業者を決める、見積もりを取る

引越しは12月末や新年度の3月~4月上旬にピークを迎えます。シーズンオフでも、土日や祝日は混む傾向にあります。
人気日は予約が取れないこともあるため、早めに引越し業者とコンタクトを取り、見積もりと予約を済ませておくことが大切です。(※)
スピーディに引越し業者の見積もりを取りたいときは「一括見積りサイト」が活躍します。
(※)近年、働き方改革の影響により、引越し業者は受け入れられる件数が減りました。
その結果、引越しをしたくても引越しができない、いわゆる「引越し難民」と呼ばれる方々が続出しました。
今後もその影響は続くことが予想されます。
希望通りの引越しができるように、引越しが決まりましたら、すぐに引越し業者に見積もり依頼するのをオススメします。
■参考:問題が深刻化 人手不足、働き方改革が影響(毎日新聞)
引越し一括見積りサイトのメリット
- 色々な業者の「料金やサービス」が比較できる
- やり取りがシンプルになる
- 値引き交渉してもらいやすい
一括見積サイトの良いところは、顧客情報を一度入力するだけで、複数の業者のサービスや値段が比較できることです。
ライバルが多いことを業者側も理解しているため、やり方次第では相場より安い値段を引き出せることもあります。
見積もりは「希望日」「エリア」「部屋の大きさ」「居住人数」「家電の数」「エレベーターの有無」「1階か最上階か」によっても異なります。
引越し業者と契約までの流れ
- 一括見積サイトに引越し情報を入力する
- 指定したメールに、業者から見積金額が届く
- 「サービスや価格」の比較をする
- 業者を決める
- 書面にて契約する
ステップ2:現在のお住まいの賃貸契約を解約
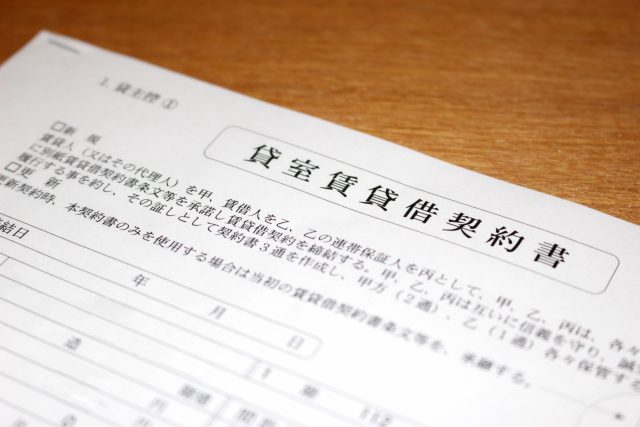
ポイント
- 管理会社に電話連絡する
- 【書面の場合】「解約通知書」を郵送で送る
賃貸マンションやアパートに住んでいる場合、管理会社に「引越します」と事前に連絡する必要があります。
部屋を借りるときに印を押した「賃貸契約書」には、退去にまつわる項目が記載されています。
一般的には「退去日の30日前に通知すること」がルールづけられています。電話で受け付けてくれるところも有るほか、「解約通知書」の記入・提出が求められることもあります。
分からない場合は管理会社に問い合わせて、退去の手続きを確認しておきましょう。
ステップ3:荷作り作業の流れとコツ

住まいの荷物は最低でも、引越し前日までに詰めておきましょう。引越し前日に終えることで、忙しい引越し当日を爽やかに迎えることができます。
荷造りのコツは大きく2つ。
「すぐ使わないモノは早めに」「直前まで使うものは、間際に詰めること」です。
メリハリを意識することで、日常生活に支障のない荷作りがおこなえます。
すっきり荷作りのコツ
■~1カ月前
スキーのセットや扇風機・こたつ布団など、シーズンオフの大物を梱包しましょう。運びやすいよう箱の下部分に重いもの、上は軽いものを入れていきます。
■~2週間前
子ども部屋のオモチャ、本棚の本・写真アルバムなど「使用頻度の低い小物」を片付けます。1年以上使っていないものは心を鬼にして、処分するのも手です。
■~2日前
キッチンの皿やお風呂場のタオルなど「使用頻度の高い小物」を片付けます。割れやすいグラスや皿は新聞紙でつつみ、緩衝材代わりにします。
■~1日前
引越し当日使いたいもの(掃除道具・紙皿・紙コップ・はさみ・タオル・ガムテープなど)の箱を作り、それ以外は全て収納します。
引越し当日までに必要な手続きリスト

■必ずやりたい、引越し前のチェックリスト
- 転出届(※お住まいの自治体で、2週間前から受付可能)
- 国民健康保険:資格喪失証明書
- ライフラインの住所変更
電気、ガス、水道、インターネット、固定電話、携帯電話、新聞 - 金融機関の住所変更
銀行、クレジットカード会社 - 子ども関係の手続き
転校と転園の異動手続き(※学校や幼稚園の窓口および自治体の区民課) - 郵便物の転送
(※郵便局の窓口もしくはネット、登録まで約1週間かかるため早めに済ませたい) - NHKの住所変更
引越し作業と同時におこなっておきたいのが、引越し前の手続きです。
特に役所関係の手続きは期間が決まっていることもあり、優先的に済ませておきたいもの。
転出届は世帯主もしくは代理人でも手続きが行えます。
また、本人確認の書類(免許証など)と印鑑が必要なことが多いので用意しておきましょう。
電気・ガス・水道などの3大ライフラインの手続きも、早めに手続をしておきましょう。
ステップ4:引越し当日の流れ

待ちに待ったお引越し。当日は引越し業者がトラックで訪れ、搬出作業をおこないます。
作業日初日に代金を支払うことが多いため、現金もしくはクレジットカードを用意しておきましょう。余裕があれば、スタッフの方の心付けや差し入れを準備しておきます。
段ボール箱が運び出されたあとは、お風呂場・ベランダなど見落としがちなスポットに、荷物の置き忘れが無いか最終確認しましょう。
当日管理会社に立ち合ってもらい「室内の状態チェック」「鍵の返却」をおこなう場合は、搬出と同時に簡単なクリーニングをすませておくと印象が良くなります。
ステップ5:引越し後の流れ・手続きなど

荷ほどきが始まると、大量の段ボール箱が出ます。新居のゴミ捨て場に出すと、近隣の方の迷惑にもつながります。
引越し業者に依頼すれば、希望日に取りに来てくれるため「引越し業者に回収してもらうこと」を頭に入れておきましょう。
ステップ6:引越し後にやること、チェックリスト

■引越し後のチェックリスト
- 転入届
(※お住まいの自治体で、引越し後2週間以内におこなう) - 学校の転入手続き
(※転退学通知書を新しい学校に提出する) - ガスの開栓手続き
(※電気や水道と異なり、立ち合いが必要) - 国民健康保険と国民年金の住所変更
(※自治体の区民課および日本年金機構) - 免許証の住所変更
(※警察署や免許更新センターにておこなう)
自治体の転入届は「引越し後2週間以内」と期間がとても短くなっています。
引越しの荷解きや疲れがまだまだ残っていてひと休みしたい時期ですが、役所や学校関係・ライフラインの手続きは待ってくれないもの。
第一優先テーマにして、早め早めに乗り切っておくと安心です。