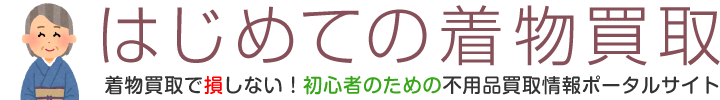引越し作業で最も面倒だといわれているものが「荷造り」です。
作業が終わらず途方に暮れたり、引越し日が近づいてくるとかなりのプレッシャーでパニックになる人も実は多いです。
ストレスなく効率的な荷造りを行うためには、「事前の段取り」と「コツをつかむ」ことが大切です。
引越しを決めてから引越し当日まで、どのように荷造りを進めたらよいかをご紹介します。
まずはじめに、梱包材と必須アイテムを準備する。

荷造りを始めるには、まず荷物を梱包するための資材が無くてはいけません。ここでは効率的な荷造りを行うための必須アイテムをご紹介します。
ダンボール
まず引越しが決まったら早めにダンボールを用意しましょう。大手引越し会社に引越しを依頼すると大抵ダンボールとガムテープは無料でもらえます。
営業担当者が家の大きさや荷物の量を確認し、おおよそ必要な枚数を用意してくれますが、引越し日直前になってダンボールが足りないなどの事態を避けるため、「少し多めにお願いします。」と伝えておくのがポイント。
ほとんどの業者は、快くダンボールを置いていってくれます。
一方、引越し業者に依頼せず、自力で引越しをする場合は、スーパーや薬局、コンビニなどでダンボールを調達することができます。
ただし引越しに適さないペラペラのダンボールが多いため、積み上げると箱の形がすぐに変形したり、引越し作業中に底が破れたりして大変な目に合う可能性がかなり高いです。
なるべく頑丈でサイズの揃ったキレイなものを選びましょう。
ネットで新品のダンボールも購入できるので、そちらもおすすめです。
おすすめダンボール3選
■イモ類やミカンなど野菜果物用のダンボール
作りが丈夫で大きさも丁度良い!※根菜類は土汚れが付いている為、汚れを取って内側に適した大きさのゴミ袋を入れてから収納すると安心です。
■2リットルのペットボトル用のダンボール
ちょうどA4サイズの書類や書籍が収納しやすく、持ち手もあって運びやすいです。丈夫であるため、重い荷物の梱包にオススメです。
■おむつ用の大きなダンボール
軽いけどカサ張る商品用なので、大きいですが薄めで形が崩れやすいです。布団類、大きめの衣類を詰め込まなない程度に入れるのに適しています。
ガムテープ(布製・色つき)
引越し業者から無料で貰う梱包用テープは、紙製のクラフトテープが多く強度に少し不安があります。
紙製テープは重ね付けができない、横から破れやすい等、実は引越しには向いていません。
重い荷物が入っているダンボールには強度のある布製のガムテープを使用した方が安心です。
また、色つきのテープを別途用意して「割れ物は赤いテープ」、「すぐ使うものは黄色のテープ」などと色分けすると引越し業者さんにも親切ですし、荷解きの際にもわかりやすくなるでしょう。
布団袋
これも引越し業者が無料でくれることが多いです。
引越し後は、来客用のお布団など出番の少ないお布団の保存用として使えますし、荷解きの際に出るガムテープやひも、新聞紙などのごみを入れる袋としても利用できます。
引越し業者を使わないで自力での引越しをされる方は、ホームセンターや100円均一ショップなどでも手に入れることができます。
布団の数も少なく専用袋を用意できない場合は一番大きなゴミ袋(90L)を2重にして使用しても問題ありません。(通気性は悪いので、引越し後は必ず梱包を解く必要があります。)
新聞紙
食器などの割れ物を梱包したり、箱の隙間に丸めて入れたりと新聞紙は引越しに大活躍します。引越しを決めたら新聞紙の保管を始めましょう。
ただ近頃は新聞をとっている家庭はかなり少なくなっています。
自宅で新聞が用意できない場合は、新聞販売店やご近所に古新聞を譲ってもらったり、新聞が置いてある喫茶店や美容室などに頼んだりして古新聞を手に入れましょう。
それほど割れ物が多くない場合は、タオルなどでくるむという手もあります。また、駅などのフリーペーパーを読んだ後、保存しておくというのもいいかもしれません。
食器類を新聞紙で包むと、クッション材とまみれたり、似たようなものが並んだりで内容物がわかりにくくなります。
新聞紙に直接、何が梱包されているかマジックで記入したり、間違って掴んでは危ないような包丁ナイフ類、お箸やフォークなどの尖ったものは、誰でもすぐに分かるように目印を付けるようにしましょう。
ビニール紐
ビニール紐はいらなくなった本や雑誌を束ねたり、すぐにばらけてしまう荷物をまとめたりする際に便利です。
ただし、引越し業者に運んでもらう本や雑誌は、結び目がほどけて荷物がばらける恐れがあるため、段ボールに入れて運搬してもらうことになりますので注意しましょう。
油性マジック
油性マジックはダンボール表記に使います。
ダンボールの中身を記入する際は、箱を積み上げた際にもわかるように、上部だけではなく側面にも記入しましょう。
はさみ、カッター
ビニール紐を使う時や割れ物を梱包する時、荷解きをする時など様々な場面で必ず必要になりますので、はさみとカッターナイフの両方を用意しましょう。
小さな子供がいる人は、荷造り作業に夢中になってその辺に置きっぱなしにしたりしないようにくれぐれも気を付けましょう。
ドライバー・六角レンチ
ラックなど組み立て式の家具を分解するときに必要となります。
大小いくつかのプラス・マイナスドライバーと六角レンチを用意しておくとかなり役に立ちます。
さらに電動ドライバーがあれば相当なスピードアップが期待できます。
軍手
引越しの荷造りを行っていると、ダンボールや紐などに触れることが多いため、手が荒れてガサガサになってしまいます。
また、手を切ったり怪我をすることも多いので必ず軍手を用意しましょう。
荷造りは薄手の手袋、荷物運搬は滑り止めの付いた軍手などと分けるとよいでしょう。
ゴミ袋(小・大)
荷造りをすすめると処分するものがたくさん出てくるので、ごみ袋は小さいものと大きいものを用意しておきましょう。
洗剤などの液体をダンボールに入れる際には、水漏れしても大丈夫なようにゴミ袋に入れてからダンボールに入れると安心です。
ポリ袋(小・大)
透明で衛生的なポリ袋は、細かい物をまとめるのに重宝します。
家具のネジ類は外した後、ポリ袋に入れて家具にガムテープで貼り付ければ紛失しにくく、組み立てる時に探す手間も省けます。
コード類は丸めて小さめのポリ袋に入れるとコンパクトにまとめられます。
「何のネジなのか?」「何のコードなのか?」も直接記入できるので、整理しながら梱包できるのでオススメです。
ぞうきん
荷造りの際に家具に溜まったほこりや汚れをふき取ったり、室内の掃除で使用したりと、なにかと重宝するので多めに用意しておきましょう。
◇
以上が引越しの荷造りに欠かせない資材、備品となります。
ガムテープや油性マジック、軍手などは作業をする人数分を用意しておくと、探し回るストレスと無駄な時間を削減することができ、効率的に作業を進めることができます。
荷造りはスケジュールを立て、計画的に。

引越しが決まったら荷造りのスケジュールを立てることが肝心。
引越しの作業は大きく分けて「荷作り」と「手続き」です。
家の大きさや荷物の量によりますが、たいていは想像以上に荷物はあるものです。その分荷作りには時間がかかります。
荷作りは引越し前日にはほぼ完了していなくてはいけません。また日用品も梱包するので、そのせいで引越し日までの生活が不便になっても困ります。
その為、何をどの段階で梱包するか、スケジュールを把握することが大切なのです。
また、引越し当日の作業効率を下げる要因の一つは、「どの荷物がどこの部屋に行くのか」がわかりにくくなることです。
荷物は使う部屋に直接運び入れ、荷解きもスムーズに行えるよう、荷作りの段階で準備しておけば、スムーズに新生活がスタートできます。
STEP1 少しずつ荷物の整理を始めよう(引越し日決定直後、もしくは2週間前から)
荷造りのコツは、普段使わないものからすぐに梱包を始めてしまうこと。そして引越し間近に普段よく使っているものを片付けていきます。
すぐに使わないものであれば、引越しが決まった直後から梱包して問題ありません。季節外れの衣類、来客用の食器など。
「もしかしたら急に使うことになるかも?」というものは、ダンボールをガムテープで閉じずに積んでおけばいつでも取り出せます。
ダンボールに荷物を入れたら必ず、何が入っているかを上面と横面に記入しておきます。
また荷造りが進み過ぎて、気がついたら荷物で出入口がふさがってしまったり、あちらこちらに山積みされたダンボールがあると生活が不便ですし、効率的な荷造りもできません。
一箇所を荷物を積む場所と決めて、まとめておきましょう。
あまり使っていない部屋、クローゼットの中でも良いですし、荷物を梱包したことで空きができた場所にダンボールを入れておくのもオススメです。
STEP2 不用品の処分する
引越しが決まったらすぐに始めてほしいのが「不用品の処分」です。
まずはクローゼットや押し入れの中の衣服や家電などの整理から始めて、売れそうなものはまとめて売ってしまいましょう。
廃棄するものはごみの日に合わせて効率よく廃棄し、粗大ごみとなるものは早めに引き取りの手配を行っておきます。
まだ使えるものをリサイクル業者にまとめて引き取って貰うのであれば早い(申し込みから引取まで1~3日程度)ですが、市区町村の粗大ごみは申込みから搬出まで、予約状況によりひと月かかる場合があります。
特に年末、年度末は他の人も利用するので空きがないことが多いです。その為、早めに何を廃棄するかを決め、申込みを行う必要があります。
また、引越し当日まではゴミが出るので、ごみ袋は何枚か荷造りせずに残しておきましょう。
荷造りの段階で荷物をいかに減らせられるかで、引越し後の荷解きの効率も上がってきます。さらに荷物の量を減らすことができれば、引越し料金も安くなります。
まだ廃棄前でも、引越し業者の見積もりの際に「処分予定」と伝えることで正確な見積もりをとることができます。
かさ張る本や書類は、PDF化で劇的に減らせます。
本や雑誌、書類関係は重い上にかさ張ります。
どうしても読みたい本、辞書など索引が必要な本以外は、スキャン代行会社に送付してPDFファイルにしてもらうと、荷物をかなり減らすことができます。
雑誌、文庫本、テキストなど、書籍の種類で値段は異なりますが、1冊につき100円程度でPDF化してもらえます。
※書籍によってはスキャンが禁止されている著者のものがあるので、スキャン代行会社に確認を求めるようにしましょう。
筆者は200冊以上の本をPDFにしてパソコンやタブレットに入れましたが、特に不便はありません。むしろ、旅行などで手軽に本を数十冊も持って行けるようになって便利になりました!
他にも、捨てるに捨てられない読む機会の少ない家電の説明書などは、メーカー公式サイトからPDFファイルをダウンロードできる場合があるので、保存しておきましょう。
この時、巻末などに保証書があるものは、切り取って保管しておきましょう。
冊子・雑誌をスキャンしたり書籍をPDF化すれば、ダンボール一箱分は減らせることができます。
書籍は本のままで読みたいという方にはオススメできませんが、パソコンで見ることが苦でなければ、この方法は荷物がかなり減らせるのでオススメです。
STEP3 引越し間近の梱包
引越しの直前まで使っていたものは、引越ししてからもすぐに必要となるものがほとんどです。
トイレットペーパーやティッシュ、洗面用具などの生活用品、パジャマや下着、必要最低限の食器などはまとめてダンボールに入れておきましょう。
また、新居についたらすぐに掃除機が必要になります。掃除機は最後に荷造りし、軍手、ぞうきん、カッター、はさみなどの用具と合わせて最初に荷解きするダンボールと一緒にまとめておくと便利です。
全て梱包できたら、最後に記入漏れや荷造りのし忘れがないか入念にチェックします。
ヒモ掛けの荷物や袋詰めの荷物などは、引越し当日に引越し業者さんからダンボールに入れるよう指示されますので、事前にダンボールに入れておいてスムーズな荷物の運び出しができるよう準備しておきましょう。
自分で荷造りするが難しいなら、荷造りサービスを利用する

自分で荷造りをする時間がほとんどない場合は、引越し作業の負担を大幅に軽減できる荷造りサービスを利用するのも手です。
小さな子供がいたり妊娠中にはスムーズには出来ないでしょうし、荷造りは思っている以上に時間と労力を使います。
まわりの協力があまり得られない場合であれば、荷造りサービスだけでなく荷解きサービスも含めて依頼することも検討してみてましょう。
荷造りサービスを利用する場合、引越し業者に見積もりを依頼する際に伝えておきます。
荷造りをしてくれる作業員の人件費も上乗せされるため、値段はやはり高くなってしまいます。
ですが、複数の引越し業者から相見積もりを取ること(※)で、各社の営業担当者が他社に負けないように値段を下げてくれることが多いので、初めに提示された金額より大幅に費用を抑えられることもあります。
引っ越し見積りで浮いたお金を荷造りサービスに回すことができれば、負担なく荷造りを依頼することもできますので、ぜひ試してみてください。
(※一括見積りサイトを利用すると、引越し料金の最安値がカンタンにわかります。)